【板書の色の使い分け】
どうも、野本です。
今回は、至極普通のタイトルです。
奇抜なタイトルを期待していた方、
何か、スイマセン。
変なものしか思い付きませんでした。
。。。_| ̄|○
故に、今回は普通のタイトルで
攻めたいと思います。
さて、ブログを読んで下さるあなたは、
板書の色分けをどう変えていますか?
前回に続き基本中の基本の内容ですが、
割と、色分けの統率がとれていない、
そんな方って多い気がします。
当たり前ですが、
ノートは後で見直すために取るものです。
見直したとき、その単元のテーマ、
重要部分が思い出せるよう、
工夫しなければなりません。
黒板を使う集団指導では切り離せない
テーマですので、
今回は、基本と分かっていても
板書の色使いを振り返りたいと思います。
『白色』
もちろん、普通の文章を書くとき。
※ホワイトボードでは黒を代わりに使う。
『黄色』
強調部分で使う。
→穴埋めや、重要語句のとき。
※ホワイトボードでは青を代わりに使う。
『赤色』
下線を引っ張ったり、
重要語句を更に囲んで強調するとき。
※見えずらいので、
基本、語句や文章は書かない。
『青』
更に色分けしたいとき。
個人的には、
テスト頻出の人物名は青で囲み、
覚えて欲しい年号や記述部分は
波線を引き、チェックを入れます。
※見えずらいので、
基本、語句や文章は書かない。
更に私の場合は、
その単元で最重要語句かつ
テーマになる単語は、
爆発マーク(赤)で囲んでいます。
また、
単語のテスト頻出度に応じて、
①頻出:囲む
②普通:下線
③低い:そのまま
など、3段階に分けています。
(基本、穴埋め箇所は全て
覚えるべきではありますが…。)
これは、初めは精度が低いかも
しれませんが、
多くの問題を解いていく中で、
徐々に精度が上がっていくはずです。

少し省略しましたが、
即興で書いて見ました。
参考にしていただければ幸いです。
それでは、今回はこの辺で。
このブログを読んで下さる方々に
最大の敬意を込めて。
あなたの生徒が輝く授業を
最大限していきましょう。
ありがとうございました。
メルマガを配信しています。
私の記事が面白い、役に立つと感じていただけたなら、
ぜひ、こちらもよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
無料メールマガジンの登録は画像をClick!
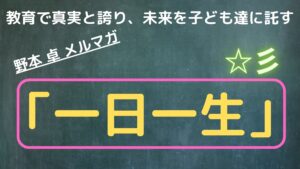
メルマガ登録特典もご用意しています。
社会科講師としてさらに成長するために必須
のアイテムです。
ぜひ手に取っていただき、さらに成長・飛躍を遂げ、
生徒や保護者から厚く信頼され、
明るく充実した日々を過ごしましょう!



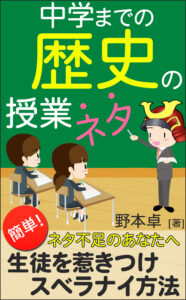

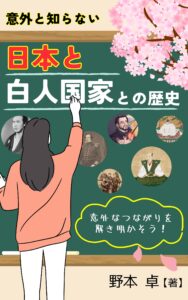
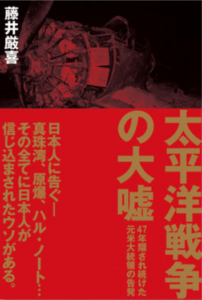
最近のコメント