Contents
【一般論とは真逆!】少子化・人口減少と社会保障の真実
どうも、野本です。
今回は若干トレンド系の内容です。
少子化・人口減少による社会保障の負担が増えると言われていますよね?
「〇人で一人の高齢者を負担~」とかいうアレです。
ですがコレ、全く根拠の無いお話なのです。
今回はそのようなお話になります。
よろしければ今回もお付き合い下さい<(_ _)>
➀ 少子化・人口減少の背景
日本の少子化は、今や社会全体が共通認識として抱える課題になっています。
出生数クイズ
突然ですが、ここでクイズです❓🎩❓
2024年の日本の出生数は何人でしょうか?➀~➂から選んで下さい。
➀75万8631人
➁68万6061人
➂53万1085人
・
・
・
(考え中)
・
・
・
はい、いかがでしょうか。
正解はぁぁ~~、、、ジャジャン🎵『➁68万6061人』でした!!
2024年の日本の出生数は68万6061人で、初めて70万人を下回りました。
1970年代には年間200万人近くが生まれていたことを考えると、この半世紀で日本の出生数は3分の1以下にまで減少したことになります。
ちなみに、➀は2023年の出生数、➂は2024年の鳥取県の人口です。
少子化の背景
なぜ少子化が進んだのでしょうか。背景にはいくつもの要因があります。
-
結婚する人が少なくなっていること
女性の高学歴化・社会進出が進み、結婚が必ず通る道ではなくなりました。その他、非正規雇用の増加や経済的不安定さも、若い世代が家庭を持ちにくい環境要因になっています。
-
教育費や生活費が高く、子どもを育てる負担が大きいこと
子育てにかかる経済的・精神的な負担が大きいことも見逃せません。教育費の高騰、保育所不足、住宅費の高さなどが重なり、「子どもを授かることが贅沢」になりつつあるのです。
-
働き方やライフスタイルの変化で、「子どもを授かるのが当たり前」という考えが弱まったこと
価値観が多様化していますよね。かつては「子どもを授かるのが当たり前」と考えられていましたが、現在では「子どもがいない生き方」や「結婚しない選択」も広く認められるようになりました。これは良い意味では社会の自由度が増したことの表れでもあります。
こうした背景が重なり合い、日本は先進国の中でも最も急速に少子化・人口減少が進む国となったのです。
➁ 少子化・人口減少が何を引き起こすと言われているか(一般論)
少子化や人口減少に関するニュースを耳にすると、多くの場合「危機」と結びつけられて語られます。一般的には、次のような論調がよく見られます。
-
労働力人口の減少
働く人が減れば、生産活動が縮小し、日本経済は衰退する。 -
経済規模の縮小
人口が減ることで国内市場が縮小し、消費が減り、企業の成長が難しくなる。 -
社会保障の維持困難
高齢者が増える一方で支える若者が減るため、年金・医療・介護が立ち行かなくなる。 -
地方の過疎化
人口減少が地方で特に深刻に進み、地域社会の維持が難しくなる。
これらの主張は一見するともっともらしく聞こえますし、政府やメディアも繰り返し同じフレーズを用いるため、多くの人が「少子化=危機」という図式を当然視しています。
しかし、本当にそうなのでしょうか。
➂ 一般論はデマ、キーワードは「生産性の向上」
実は「人口が減れば必ず経済が衰退する」という考え方には、大きな誤解があります。
ここで注目すべきは 「生産性」 です。
大事なことですので、もう一度述べます。
ここで注目すべきは「生産性」です。
経済成長を左右するのは、必ずしも「人口の数」ではありません。むしろ重要なのは「一人あたりがどれだけ効率的に付加価値を生み出せるか」です。
たとえば同じ100万人の労働力でも、生産性が2倍になれば結果的に200万人分の経済成果を生み出すことができます。
-
ロボットやAIによる自動化
日本はすでに人口減少社会に入っていますが、その一方でDX(デジタル・トランスフォーメーション)、AI、ロボット、自動化技術が急速に進展しています。これらは「少ない人手でも大きな成果を出せる社会」を実現する可能性を持っています。
こういう変化って働き方にも大きく影響しますよね。少し話が逸れるかも知れませんが、リモートワークの環境がさらに整備されれば、大都市への過剰な人口集中を避けることもできます。ちなみに今回の記事は、仕事をしに時々訪れる結構お洒落なカフェ☕で投稿しました(←迷惑な客?)。
-
高度な知識やスキルを持った人材の活躍
少子化の進行によって人材の価値が高まり、一人ひとりがより大切に扱われる社会になることも考えられます。賃金の底上げや教育への投資が進み、結果的に「少数精鋭型の社会」が形成されれば、むしろ経済の持続可能性は高まります。
つまり「人口が減るから経済は終わり」というのはデマであり、正しくは「人口減少をどう活かすか」が問われているということです。
➃ 社会保障が支えられなくなる!のウソ
「少子化によって社会保障が支えられなくなる」とよく言われていますが、これって本当なのでしょうか?
社会保障制度は賦課方式と言われています。現役世代が高齢者を支えているというアレですね。ですが、この話自体がそもそも事実とはちょっと違うのです。
では、ここでまたクイズです🕊🎩🕊
社会保障給付費は何でまかなわれているでしょうか?➀~➂から選んで下さい。
➀社会保険料
➁社会保険料+消費税
➂社会保険料+国債
・
・
・
(考え中)
・
・
・
はい、いかがでしょうか。
社会保障給付費は社会保険料と国債発行でまかなわれています。
ですから、現役世代どうこうというお話だけではありません。
社会保険料が減ったら、国債発行額を増やせば全く問題ないのです。
もし良かったら、とても参考になるブログです。ご覧下さいませ<(_ _)>
▼三橋貴明オフィシャルブログ「新世紀のビッグブラザーへ blog」▼
https://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12894892224.html
一般論を単純に鵜呑みにしてしまえば、「支える側が減って、支えられる側が増える」ことで破綻するように思えます。
「社会保障が破綻する」と強調される背景には、しばしば政治的な意図があります。財務省や一部の経済団体は、国民に「将来の不安」を意識させることで、増税や制度改正を受け入れさせやすくしているのです。消費税増税なんかがその典型例ですね。
冷静に考えれば、社会保障制度は国民生活を守るための基盤であり、国家が放棄することはあり得ません。制度の形は変わるかもしれませんが、「支えられなくなる」というのは過度な危機論であり、誤解だと言えるでしょう。
おわりに:少子化は「危機」ではなく「転換点」
いかがでしょうか。
少子化・人口減少は確かに大きな変化ですが、それを「危機」として煽るだけでは解決にはつながりません。
むしろ私たちが注目すべきは、「どうすれば日本が持続的に成長していけるか」という視点です。
ちなみに今回の内容が分かれば、人口減を理由に移民を受け入れるのがどうして良くないのかなども分かってくると思います。(純粋な日本人が増えるのは良いと思いますが…。)
少子化の現実を直視しつつ、生産性向上や働き方の改善、制度の柔軟な改革を進めれば、日本は新しい形の安定した社会を築けるはずですし、人口の問題にしても修正をはかっていけるでしょう。
では、今回はこの辺で。
このブログを読んで下さる方々に
最大の敬意を込めて。
あなたの生徒が輝く授業を
最大限していきましょう。
ありがとうございました。
メルマガを配信しています。
私の記事が面白い、役に立つと感じていただけたなら、
ぜひ、こちらもよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
無料メールマガジンの登録は画像をClick!
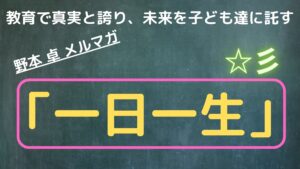
メルマガ登録特典もご用意しています。
社会科講師としてさらに成長するために必須
のアイテムです。
・確認テストテンプレート(一問一答形式)
・記述問題テンプレート(問題用紙と解答用紙)
・集客を伸ばすための勉強コラムチラシ
・参考になると幸い!模擬授業音声
※他にも良いものがあればアップします!
ぜひ手に取っていただき、さらに成長・飛躍を遂げ、
生徒や保護者から厚く信頼され、
明るく充実した日々を過ごしましょう!
※紹介文をご覧いただく必要がない方は、
コチラからご登録下さい<(_ _)>
↓↓↓↓↓



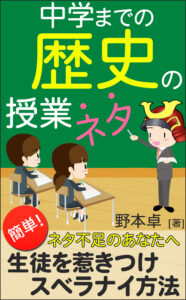

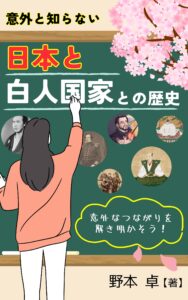
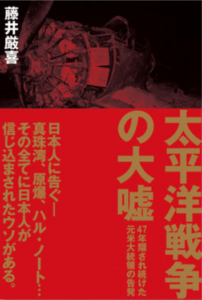
最近のコメント